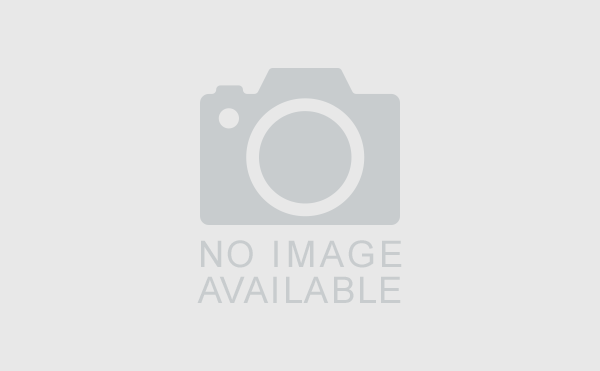相続は、早い者勝ち?
相続法改正前(令和1年6月30日まで)
特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言があった場合には、当該遺言において相続による承継を当該相続人の意思表示にかからせたなどの特段の事情のない限り、何らの行為を要せずして、当該遺産は、被相続人の死亡の時に直ちに相続により承継される(最判平成3年4月19日、民集第45巻4号477頁)。
→遺言書の効力が絶対でしたので、法定相続分を超える遺産を取得する場合でも、相続登記を急ぐ必要はありませんでした。
相続法改正後(令和1年7月1日から)
相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、(法定)相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない(民法第899条の2)。
→法定相続分を超える遺産については、登記を先にした方が優先されます。
<具体例>
(前提)
相続人:長男A、長女B
遺言書:土地及び建物は、長男のAに相続させる。
Bが相続登記(持分2分の1A、持分2分の1B)をし、Bの持分だけを第三者Cに売却。
→BがC売却した土地建物の持分2分の1は、C所有になってしまいます。つまりAとCの共有(いっしょに持っている)状態になります。
対策はありますか?
<被相続人死亡後>
遺言書がある場合は、四十九日や一周忌を待たず、すぐに相続登記をしましょう。
<被相続人死亡前>
1.公正証書遺言や法務局における自筆証書遺言の保管制度を利用しましょう。
法務局に保管しない自筆証書遺言は、家庭裁判所にて検認手続(遺言書の開封作業)が必要です。戸籍取得の手間や郵送手続き等で、また新型コロナウイルス感染症の影響で裁判所の手続きに時間がかかる場合があります。公正証書遺言や法務局における自筆証書遺言の保管制度を利用することにより、登記手続きまでの時間を短縮することができます。
2.判断能力が残っている場合には、生前贈与をしておきましょう。